理学療法学科
理学療法学科
国家試験合格状況

今年度の結果をお知らせします。
全ての学科で全国平均を上回ることができました。
合格された皆さんおめでとうございます!
本校合格率
理学療法学科 100%
全国平均
理学療法学科 89.2%
理学療法学科のオープンキャンパス
リハビリの仕事まるわかりコース

理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科の3学科のことはあまりわかっていない、という人にはおすすめのコースです。
学科別体験コース

どの学科を志望すると決まっている人や2回目以降の参加におすすめのコースです。
受験対策コース
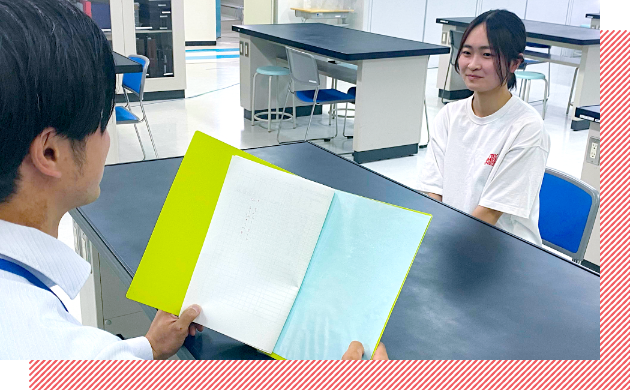
AO入試に必要な書類、願書作成のコツ、面接で押さえておきたいポイントなど、2回目の参加や受験を考え始めたら、受験対策コースがおすすめです。
放課後コース

3学科のリハ体験を通して、関連職種に対する理解を深めて頂きたいと考えています。
個別相談コース

専任教員が学校の魅力、3学科の専門性の違い、入試対策、学校周辺の環境など幅広く1対1の個別相談の形式でご説明させて頂きます。AO入試のエントリー資格を得られます。
様々な疾患や障害に適した、効果的な治療法を学ぶ
理学療法とは、病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある方(または、低下すると予想される方)に対し、医師の指示のもとに運動療法や物理療法(電気、温熱など)を用いて治療を行います。
主に基本的動作(寝返り、起き上がり、座位姿勢、立ち上がり、立位姿勢、歩行)の回復を図り、生き生きと生活できるようにサポートする役割を担います。
理学療法士の活躍の場は医療現場だけでなく、運動機能低下が予想される高齢者の予防対策、メタボリックシンドロームの予防、スポーツ分野でのパフォーマンス向上など障害を持つ人に限らず、健康な人々に広がりつつあります。
また、運動・動作の専門家としての立場から、福祉用具や、住宅改修に関する相談対応も行います。

厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の元「理学療法」を行う療法士。
理学療法士作業療法士養成施設(専門学校など)で、3年以上学び、卒業または卒業見込みの者が国家資格の受験資格が得られます。
平成リハが選ばれる理由
勉強が安心
充実した個別サポートで高い国家試験合格率
費用が安心
学費が安くサポート制度も充実
実習が安心
グループ病院との連携
将来が安心
全国から多数の求人
教員紹介

先生の話

専門:運動療法学
2015年から平成リハビリテーション専門学校の教員として理学療法分野を指導。教鞭を執る傍ら、大阪市立大学大学院 医学研究科で医療統計学を学び、修士課程を修了。
先生の取組み内容
私が教えている「運動療法学」は、理学療法のベースになるもので、座学と実技の両方の授業を担当しています。特に1年生の実技では、筋力増強や関節可動域拡大、動作改善などの運動療法を具体的かつ視覚的にわかるように工夫することを意識して指導しています。
他にも「運動学実習」では動作分析を指導。最初に患者さんの動画を見てもらい、その後、学生に患者さんの真似をしてもらって、通常の人の動作と比較しながら、その違いから「このような症状の時、患者さんの動きはこうなる」という気づきを与えて分析力を育むと共に、患者さんが感じる苦しさもイメージできるようにしていますね。私の授業を通して、患者さんの症状を深く理解する力を身につけ、患者さん一人ひとりに寄り添ったリハビリテーションができる理学療法士に成長してくれたら私も嬉しいです。
授業・ゼミの雰囲気
先生の豊富な臨床現場での経験を聞き、リアルに学べる「運動療法学」
「運動療法学は、臨床現場では理学療法士として患者さんの状態を把握、分析する際に役立つもので、その後のリハビリテーションメニューを考えていくための土台となります。そうした観点から私の授業では、ただ知識を教えるのではなく、学生自身が体を動かして五感で感じることで、患者さんの立場で考える力を育むようにしています」と先生。そのお話の通り、先生の授業では、学生が患者さんの気持ちを理解できるような体験と、先生の豊富な臨床現場での貴重な経験も話され、色んな患者さんがいることをリアルに感じられるとのことでした。キミへのメッセージ
理学療法士になる夢を絶対に見捨てず、一緒に叶えるまで支える学校です!
平成医療福祉グループが大切にしている「絶対に見捨てない」という理念は、本校においては「学生を見捨てない」ということだと私は捉えています。本校では私だけでなく、先生全員が学生の夢が叶うまで応援しますよ!カリキュラム
医学の基礎知識を土台に、理学療法士として必要な専門知識および技術を習得し、総合的な視野を持って臨床の場で活かせる力を育成できるよう、十分な実習時間を確保したカリキュラムを編成しています。
学べること
1年次
基礎科目(生命倫理学・臨床心理学など)と主要な専門基礎科目(解剖学・生理学・運動学など)を履修します。臨床の場で必要とされる医学の知識は幅広いため、専門領域を学ぶ前に基本となる医学的基礎知識や関連領域をじっくりと学びます。
2年次
専門基礎科目と専門科目を履修します。リハビリテーションの対象となるさまざまな病気の成り立ちや症状の他、理学療法士に必要とされる検査/評価の仕方、アプローチの方法などの知識/技術を学びます。またそれらの実践の場として前期には評価実習Ⅰ(2週間)、後期には評価実習Ⅱ(3週間)を行います。実習指導者からの指導も得て、それまでに学んだ知識/技術を患者さんの状態に合わせて実践していく力をつけていきます。
3年次
前期に総合実習Ⅰ(9週間)と後期に総合実習Ⅱ(9週間)を行います。指導を受けながら患者さんの評価を行い、治療計画を立てて実践することにより、来春から理学療法士として働くことが出来るように自身を磨きます。2回の総合実習が終われば2月まで、国家試験に向けての総復習が始まります。その内容は多岐に及ぶので、1年次・2年次からの地道な学習が大切になります。
理学療法学科カリキュラム
基礎科目
| 科学的思考の基礎 | 情報処理学 情報リテラシー 生物学 生命倫理学 臨床医学英語 |
| 人間と生活 | 臨床心理学 ソーシャルワーク概論 |
| 社会の理解 | コミュニケーション論 |
専門基礎科目
| 人体の構造と機能及び心身の発達 | 骨・関節学 解剖学Ⅰ 解剖学Ⅱ 解剖学実習Ⅰ 解剖学実習Ⅱ 生理学Ⅰ 生理学Ⅱ 生理学実習Ⅰ 生理学実習Ⅱ 人間発達学 運動学Ⅰ 運動学Ⅱ 運動学Ⅲ 運動学実習Ⅰ 運動学実習Ⅱ 運動学実習Ⅲ |
| 疫病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 公衆衛生学 内科学Ⅰ 内科学Ⅱ 整形外科学Ⅰ 整形外科学Ⅱ 神経内科学 小児科学 スポーツリハビリテーション学 精神医療 脳神経外科学 医学概論Ⅰ(病理・救急・画像診断) 医学概論Ⅱ(薬理・栄養) |
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | リハビリテーション概論Ⅰ リハビリテーション概論Ⅱ |
専門科目
| 基礎理学療法学 | 基礎理学療法概論Ⅰ 基礎理学療法概論Ⅱ 基礎理学療法概論Ⅲ 基礎理学療法学Ⅰ 基礎理学療法学Ⅱ 基礎理学療法学Ⅲ 基礎理学療法学Ⅳ 基礎理学療法学Ⅴ 基礎理学療法学Ⅵ 基礎理学療法学Ⅶ |
| 理学療法管理学 | リハビリテーション管理学 |
| 理学療法評価学 | 理学療法評価学Ⅰ 理学療法評価学Ⅱ 理学療法評価学Ⅲ |
| 理学療法治療学 | 運動療法学Ⅰ 運動療法学Ⅱ 運動療法学Ⅲ 運動療法学Ⅳ 運動療法学Ⅴ 運動療法学実習Ⅰ 運動療法学実習Ⅱ 運動療法学実習Ⅲ 物理療法 物理療法演習 義肢装具学 義肢装具学演習 日常生活活動 理学療法技術論 理学療法技術論演習 |
| 地域理学療法学 | 地域理学療法論Ⅰ 地域理学療法論Ⅱ |
| 臨床実習 | 実習対策Ⅰ 実習対策Ⅱ 実習対策Ⅲ 見学実習Ⅰ 見学実習Ⅱ 評価実習Ⅰ 評価実習Ⅱ 総合臨床実習Ⅰ 総合臨床実習Ⅱ |
講義紹介
| 1年次基礎理学療法概論 | 理学療法についての基礎から、理学療法士の役割・対象者など、幅広く学びます。 |
| 1年次運動学 | 理学療法を行う上で基本となる学問となります。人間の運動器を学び、身体運動を理解します。 |
| 2年次物理療法 | 温熱や電気などの物理エネルギーを用いて、その特徴を生かした治療方法を学びます。 |
| 2年次運動療法学 | 身体運動を行うことにより障害の軽減・回復を目指すことを目的とする治療法を学びます。どのような疾患の方に対して実施するべきかなのかを学びます。 |
| 2年次理学療法評価学 | 体が動きにくい状態がどの程度なのか、関節の動く角度や筋力、しびれなどの有無、起き上がりや歩行動作の観察など様々な検査・評価の方法を学びます。 |
| 2年次理学療法技術論 | それぞれの疾患や障害に応じた治療技術を学びます。 |
| 3年次特別講義 | 様々な分野の臨床で活躍されている先生方から実際に講義を受けます。 |
学生の声

尼崎小田高等学校 卒
学校で学んでいること・学生生活
理学療法の見学実習で、病院や施設で臨床現場を見学することに全力投球中。何らかの障害がある子どもから高齢者までの幅広い患者さんや利用者さんにリハビリテーションを行っている現場を実際に見学しています。なぜ歩けないのか、立ち上がれないのかそれ以外にも身体の構造を授業を通して深く学び、知ることができました。これから叶えたい夢・目標
高校1年生から理学療法に関心を持ち始めました。今は、ToDoリストを作成し、復習する教科の確認や一日のスケジュールを把握できるように意識しているんですよ。これからは、理学療法士になるための基礎的な知識だけではなく、応用的な知識も理解できるようにしていきたいと考えています。この分野・学校を選んだ理由
先生と学生の距離が近く、学生のために親身になって相談に乗ってくれたことに一番魅力を感じ本校への入学を決めました。1年次から実習があり、理学療法士として必要な知識や技術を学べるのも大きなポイントですね。分野選びの視点・アドバイス
縦の繋がり、横の繋がりがあることがとても魅力的ですね。本校で学ぶことによって日々、新しい自分になれると思います。入学したら、ボランティアに参加するようおすすめします。1週間のタイムスケジュール
月
火
水
木
金
1限目
09:00-
10:30
—
理学療法
概論Ⅰ
臨床心理学
―
解剖学Ⅰ
2限目
10:40-
12:10
運動学実習Ⅰ
生物学
運動学Ⅰ
理学療法
評価学Ⅰ
情報
リテラシー
3限目
13:00-
14:30
運動学実習Ⅰ
ソーシャル
ワーク論
生理学Ⅰ
理学療法
評価学Ⅰ
―
4限目
14:40-
16:10
生理学Ⅰ
基礎理学
療法学Ⅰ
―
解剖学実習Ⅰ
―
実習先
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限目 |
09:00- 10:30 |
— |
理学療法 概論Ⅰ |
臨床心理学 | ― | 解剖学Ⅰ |
| 2限目 |
10:40- 12:10 |
運動学実習Ⅰ | 生物学 | 運動学Ⅰ |
理学療法 評価学Ⅰ |
情報 リテラシー |
| 3限目 |
13:00- 14:30 |
運動学実習Ⅰ |
ソーシャル ワーク論 |
生理学Ⅰ |
理学療法 評価学Ⅰ |
― |
| 4限目 |
14:40- 16:10 |
生理学Ⅰ |
基礎理学 療法学Ⅰ |
― | 解剖学実習Ⅰ | ― |
| 兵庫 | 今井病院、萩原みさき病院、介護老人保健施設ヴィラ光陽、介護老人保健施設ふるさとの家、介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚、酒井病院、すずらん病院、宝塚リハビリテーション病院、田中病院、土井病院、西宮回生病院、西宮協立リハビリテーション病院、八家病院、東浦平成病院、姫路第一病院、平成病院、南淡路病院 |
| 京都 | 京都大原記念病院、京都きづ川病院、京都大学医学部附属病院 |
| 奈良 | 奈良社会保険病院 |
| 大阪 | 浅香山病院、泉佐野優人会病院、宇佐美クリニック、大阪回生病院、介護老人保健施設ホライズン、介護老人保健施設みさき 北大阪警察病院、堺平成病院、関谷クリニック、高村病院、天仁病院、豊中平成病院、名取病院、西淀病院、岸和田平成病院、平成記念病院、弥刀介護老人保健施設、弥刀中央病院、南堺病院、南大阪病院、八尾リハビリテーション病院 |
(他 多数 50音順)
就職先
| 兵庫 | おおくまセントラル病院、大山病院、介護老人保健施設プリエール、株式会社あらたか、北淡路病院、協立温泉病院、栗尾整形外科、恒生病院、神戸マリナーズ厚生会病院、笹生病院、翠鳳第一病院、高岡病院、東浦平成病院、永田整形外科、西記念ポートアイランドリハビリテーション病院、西病院、野木病院、宮地病院、吉田病院、ありがとうデイサービス、ときわ病院、政田整形外科、大隈病院、田中病院、都クリニック、あおい病院、ありがとうデイサービス、さわだ整形外科、はくほう会セントラル病院、マイライフ芦屋、伊丹せいふう病院、荻原みさき病院、協立温泉病院、三聖病院、三田リハビリテーション病院、春日病院、神戸マリナーズ厚生会病院、神戸平成病院、西記念ポートアイランド病院、西宮回生病院、西宮協立リハビリテーション病院、西宮敬愛会病院、西宮渡辺病院、青い空の郷、大原病院、南芦屋浜病院、南淡路病院、兵庫みどり苑、兵庫医科大学病院、宝塚リハビリテーション病院、放課後等デイサービスコレクト、本山リハビリテーション病院、野村医院、祐生病院、緑駿病院 |
| 大阪 | アクティブ訪問介護ステーション、一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ、上山病院、大阪回生病院、大阪市旭区医師会さくらクリニック、加納総合病院、関西リハビリテーション病院、こみ整形外科、彩都リハビリテーション病院、城東中央病院、千里リハビリテーション病院、鶴見緑地病院、春木病院、名取病院、牧リハビリテーション病院、森之宮病院、やん整形外科医院、堺平成病院、豊中平成病院、あらまき整形外科クリニック、グローバルフラット、なみはやリハビリテーション病院、医誠会茨木病院、井上病院、加納総合病院、河村医院、岸和田平成病院、厚生会第一病院、坂本病院、正和病院、西淀病院、摂津ひかり病院、中之島いわき病院、南大阪病院、日野病院、富永病院、豊中平成病院、北大阪ほうせんか病院、淀川暖家の苑、淀川平成病院、林原整形外科クリニック、和田病院 |
| 京都 | シミズ病院、十条リハビリテーション病院、洛西ニュータウン病院 |
| 奈良 | 山の辺病院、生駒病院 |
| 近畿圏外 | 平成横浜病院、JCHO(独立行政法人地域医療推進機構、世田谷記念病院、平成扇病院、緑成会病院、鳥取生協病院、きたじま田岡病院、江藤病院、のべおか老健あたご、種子島医療センター |
(他 多数 50音順)
OB紹介

あきらめなければ夢は叶う
学科/卒業年:理学療法学科/2016年卒業
勤務先:雨宮整形外科
大相撲トレーナー
―まずは理学療法士を目指そうと思った経緯を教えていただけますか。
高校で野球漬けの毎日を過ごしていたときに、ケガをしたことがきっかけでした。そのケガがなかなか治らなくて、すごくしんどい思いを抱えながら野球をしていたので「将来はスポーツを支える人になりたい」と漠然と考えていました。
―そこで理学療法士を選ばれたのでしょうか?
いえ、そのときは「理学療法士」という職業も全然知らなくて、担任の先生に「その道を目指すなら理学療法士かな」と教えてもらいました。先生に相談したことがきっかけで先生から学校も紹介してもらって「平成リハビリテーション専門学校」で理学療法士を目指そうと思いました。理学療法士を目指すことを伝えた高校の親友に逸ノ城関がいて「それだったら、専属のトレーナーになってほしい」と言われたことで、より強く想えました。彼もこれから奮闘するところだったので、僕もそれを支えたいと思いました。
―志を持って入学した学校。一番印象に残っていることを教えてください。
留年したことです(笑)。先生にも随分と迷惑をかけたと思います。ただ、留年が決まると退学する学生もいるようですが、僕はすでに逸ノ城関のコンディショニングをサポートしていたので「ここで辞めるわけにはいかない」と踏ん張りました。まだまだ半人前な僕に「卒業したら専属のトレーナーになって!」ってずっと言い続けてくれました。卒業が当初の予定よりも延びてしまったなかでも、専属のトレーナーになるからがんばろうって思いながら卒業まで走り切った感じです。
―卒業後からトレーナーとして活動されていたのでしょうか。
いえ、1年ほど神戸にあるデイサービスや訪問看護などを提供する施設で働いていました。社会人としての基礎というか…患者さんをどう診るのか、どうやってサポートしていくのか、伝えるための準備や心得などを指導いただきました。「一生懸命働く」ってこういうことか〜! って思いました。学生のときよりも必死に勉強しましたし、学べてよかったと思っていたときに「で、夢はどうするの?」って上司に聞かれて「チャレンジしたいです!」と。そのあとは、東京に出て今の職場に在籍しながらトレーナー活動をしています。

―東京でトレーナーとして活動を始めていかがでしたか。
最初は逸ノ城関のトレーナーとしてサポートをしていました。彼が所属する部屋にはほかにも力士が所属しているので、ときどき別の力士のサポートもしていました。手探りなところも多くて、勉強会を見つけては参加したり、テーピングの巻きかたをもう一度勉強したり資格を取ってみたり…いろいろと基礎を見直していた時期もありました。
―横綱 照ノ富士のトレーナーになったきっかけも教えていただけますか?
力士をサポートする機会が増えていくなかで、照ノ富士本人からオファーが来て、照ノ富士のトレーナーになりました。連絡があった時期は、ケガの影響が一番深刻だった序二段のときです。当時は膝を少し曲げるだけでも相当つらく、成績も落ち込んでいた時期でした。
―トレーナーとしてケガに苦しむアスリートと向き合うときは、どのような心境なのでしょうか。
僕自身もケガの影響で苦しむ体験があるので、トレーニングやリハビリには、そういう不安を打ち消すだけの納得できる理由があることを伝えています。「ここが原因やから、鍛えるべき」って伝えたところで、そのメニューをこなすのはケガをしている本人。「本当に意味があるのか?」とか「なんで?」っていう問いには全部答えられるように臨みます。実際に、「ここが使えてないからです!」って言い切って、その場で体感してもらえると本人もすんなりと納得してリハビリの質も上がります。あとは、気になることがあれば真っ先にトレーナーに聞いてくるので、そこで何でも答えられるようにしっかりと準備しておきます。
―理学療法士を目指そう、スポーツに関わりたいと思っている学生さんに向けて一言お願いします!
きつい言い方になってしまいますが、なまぬるい気持ちでは目指せない道だと思います。「どうしてもなりたい!」という強い気持ちを持っていないと、状態が悪いアスリートの治療に携わることはできません。一般的な患者さんでいう「リハビリ」のメニューとは全く異なりますし、経過が重要視されることはなく、アスリートは結果がすべてです。だからこそ、支えたいと思う気持ちが強い方がいれば、諦めずに目指してほしいと思います。
理学療法士と作業療法士の違い
理学療法士と作業療法士は、どちらも医療従事者の国家資格で、身体や精神に障がいを持つ人に対して、その機能の回復や改善を促すリハビリテーションを行う職業です。しかし、その対象やアプローチ方法には、いくつかの違いがあります。
理学療法士
理学療法士は、主に身体に障がいを持つ人を対象としています。具体的には、脳卒中や脊髄損傷、骨折、関節疾患、がんなどの後遺症や、老化による機能低下などによるものです。主に身体機能の回復や改善を目的としたリハビリテーションを行い、具体的には、運動療法、物理療法、水中療法、装具療法などが行われます。
作業療法士
作業療法士は、身体だけでなく精神にも障がいを持つ人を対象としています。具体的には、発達障害や精神障害、認知症などの後遺症や、高齢による機能低下などによるものです。主に日常生活動作の回復や改善を目的としたリハビリテーションを行い、具体的には、作業療法、生活指導、心理療法などが行われます。
アクセス
平成リハビリテーション専門学校は、大阪と神戸のちょうど中間に位置する西宮にあります。近くに大学がたくさんある学生の町です。学生用マンションなどもたくさんありますので、遠方の方でも安心してお越しいただけます。
663-8231 兵庫県西宮市津門西口町2-26
TEL:0798-38-1288/FAX:0798-38-1289
JR神戸線 西宮駅/南へ徒歩約5分
阪急電車 西宮北口駅/阪急バスでJR西宮駅まで約15分
阪神電車 今津駅/西へ徒歩約8分
阪神電車 西宮駅/東へ徒歩約8分
阪急電車 今津駅/西へ徒歩約8分
JR大阪駅からのアクセス
JR神戸線西宮駅駅下車(普通・快速)
阪神高速3号線神戸線
西行き – 武庫川出口約3分 鳴尾御影線交差左折 500m
東行き – 西宮出口約2分 染殿交差左折 300m
名神高速 西宮IC
神戸方面出口 今津交差右折 鳴尾御影線交差左折 500m
※ 当校に駐車場はございません。近隣のコインパークをご利用ください




